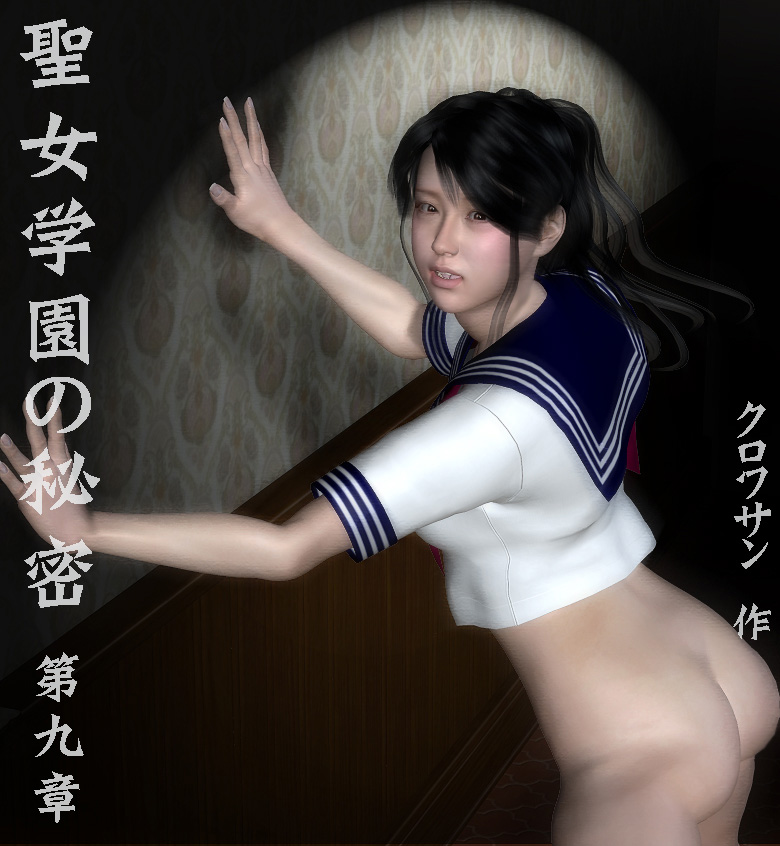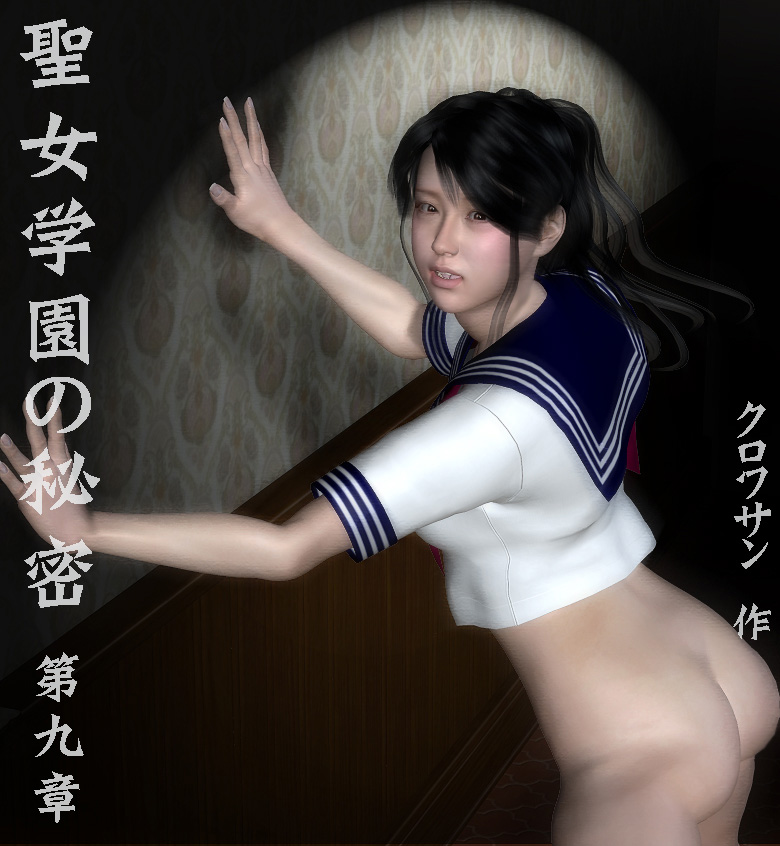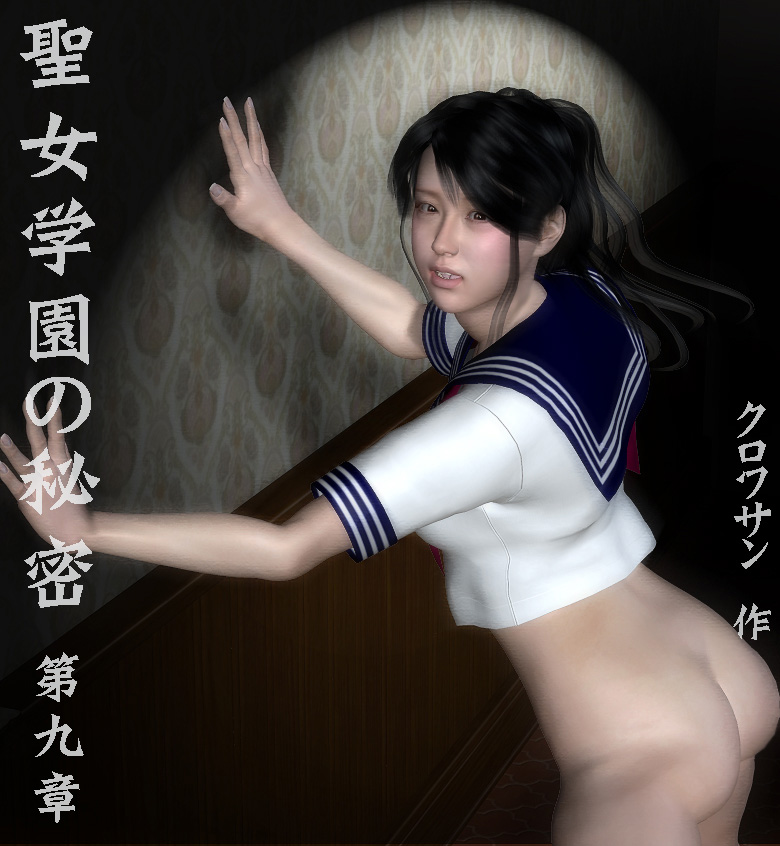第9章 廊下でもおつとめを・・・・
あれから数ヶ月経った。辛く怖ろしい肉のつとめと調教の成果で、頼子の心もからだも変化しつつあった。
ルームメイトの浅野弥生はすでに退学させられて、ある金満家に牝畜として買い取られて飼われていることが風の噂で入ってきた。
娘たちは、男子の姿を見かけると、ポオッ、と頬を染めて、甘い声をかけてスカートを胸の上までめくりあげる。廊下で、校庭で、階段で、いたるところで娘たちは全裸に剥かれ、甘い嬌声を発しつつ、からだをひらいている。
階段の踊り場で、四つん這いにされて浣腸されて喘いでいる娘がいる。庭園内で桜の木に後ろ抱きに縛られて、臀から太腿まで鞭を打たれて、泣き叫んでいる娘がいる。女子トイレの中からは、必死で許しを求める声がたえず響き渡っている。
幼い頼子は、まだ性の深淵を知らない。破瓜の後も、肉のつとめは辛くて恥ずかしいばかりだ。男子の姿をみたら、すぐにスカートを胸の上までめくりあげて挨拶するときも、ブルブル全身が震えてしまい、おねだりの声もとぎれがちであった。
それにひきかえ、ルームメイトの美樹は、すっかり牝畜化している。頼子がたじろくほど淫らで、大胆である。いつも頬を上気させ、眼の縁を朱く潤ませて全身をたえずくねらせているのは、肉交のことばかり想像しているのであろう。事実、美樹は、絶えず、《牝です、美樹は牝、お××こ専用の肉奴隷です・・・》と譫言のように繰り返し繰り返しつぶやきながら、パンティーの中に手を入れて、自ら慰めているのだ。他のクラスメートに見られても、少しも動揺することはなかった。
「あぁ、お兄さまよ、お兄さまが、こちらに来られるわ・・・・す、すっ裸になっちゃいましょうよぅ〜っ・・・」
叫ぶように、クラスメートの女子に声をかけて、脱衣する姿を、頼子はなんどとなく見かけたのである。頼子はクラスメートが手荒く犯され、仕置きされる現場も、幾度となく目撃することがあったが、とても正視に耐えられなかった。震えながら物陰に隠れて、嵐の過ぎ去るのを待つばかりだ。ところが、美樹はちかう。肉交のつとめを見ると、その場でオナニーを始めてしまうのだ。
「頼子も、人前でオナることができるようにならなきゃいけないわ・・・・美樹がこうやってオナニーしてるのは、お兄さまに見られたいからなのよ・・・・美樹がどんなにエッチお××こ好きな牝になったかを知って欲しいからなの・・・牝がまんずりしてるのをご覧になれば、お兄さまはきっと、その場ですっ裸に剥いて、からだのおつとめを果たさせてくださるはずよ・・・・・・」
美樹は頬をポオッ、と上気させながらも、先輩らしく、そう頼子に説教するのだ。傍にいたクラスメイトの由美も、恥ずかしそうに美樹に会わせる。
「頼子、お兄さまたちのお仕事は、あたしたちをお好みの牝に躾けて、仕込むことなの・・・・お兄さまのご希望に応えるためにも、どれだけご期待に応えられるような牝に堕ちているかを知っていただくことが、大切なの。あたしたちがオナニーしてるとこをご覧になれば、躾けた成果にお兄さまだって満足されるはずよ・・・・」
女子生徒は、授業中に呼び出されることもしばしばだ。外に出ると、外で待ちかまえていた男子達の手で、すぐに全裸に剥かれる。
「お、お勉強中なのにぃ〜、い、嫌な、おにいさまったらぁ〜っ・・・」
「ま、待って、由貴、い、いま、すっ裸になりますぅ・・・・」
廊下で、狂おしいまでに泣き咽んで肉交のつとめに励んでいるクラスメートたちの声がひびきわたる。
2校時目の授業中であった。
廊下から、男子生徒が音を立てて教室に近づいてきたのに気が付くと、クラスの女生徒は、ハッと青くなってブルブルふるえだす。足音が教室の前で停まると、大きな声が響いてきた。
「頼子ぉっ、出てきな。可愛がってやるからよぅ・・・・」
ひっ、と息を呑んだ頼子に、担任教師は、目を向けると、命じた。
「頼子さん、大切なからだのおつとめの時間よ。しっかりご奉仕してご機嫌をとりなさいね。今日は早退にしておきます。」
頼子は目を閉じた。逃れられない運命に嗚咽が出る。しかし、躊躇することは許されない。座席を立つと、後ろのドアを開けて外に出た。
竹刀を手にした二人の上級生が、壁に寄りかかっている。
「おにいさま、お呼びくださって、頼子、うれしいわ・・・・」
そう言いながら、型どおり頼子はスカートを胸の上までめくりあげる。
「よしよし、頼子、じゃこれからうんとふしだらなことしようぜ!」
「はい、おにいさま、頼子も、あそんでほしくって、朝からからだが疼いてたのよ・・・・」
頼子は、押し倒された。男子たちはせせら笑いながら、スカートの裾をつかまれると、頭の上までめくりあげられたうえ、頼子の頭をすっぽりと包みこむようにして、紐でしっかりと固定する。茶巾包みのような態勢だ。
視界を遮られた衝撃に、頼子は思わず、いやっ、いやぁっ・・・・と叫んでいた。
「へへへへ・・・・どうだ、頼子、茶巾は愉しいだろ?え、」
ずるずる、とパンティーが下ろされ、下半身を剥き出しにされていく。
「さ、腰上げな!」
バシッ、と太腿を叩かれて、頼子は腰をあげる。熱くたぎった太いものがズン、と入ってきた。頼子の狭い肉を強引に押し分けて入ってくる。
肉が引き裂けるような苦痛を必死で堪えながらも、必死の媚態と艶技がはじまった。
「あぁっ、あぁぁっ・・・・・いいわぁっ、おにいさまっ、いいわぁっ・・・・」
頼子はおもいっきり喜悦の声を放った。もてあそばれるとき、どれだけ悩ましく色っぽい声をたてるか、日頃から教え込まれている。意に反して犯され続ける毎日であったが、しだいに、肉の悦びを感じるからだに変わりつつあった。
「ああ、こ、これなのね・・・・これが牝の悦びなのね。」
しだいしだいに全身を貫く快美感に、頼子は気が遠くなっていく。当初は、教え込まれたとおり、必死で艶技と媚びの声をあげていた頼子であったが、しだいしだいに肉交の味を覚えつつあった。声ももはや演技とはいえなかった。
「おい、この牝、本当に感じてやがるぜ。」
「ああ、ひところは嫌がって、ヒィヒィ泣いてばかりだったが、大分味を覚えてきたみたいだな。まったく女ってやつはわからんもんだぜ、ハハハハ・・・・」
頼子には、男たちの哄笑はもう聞こえなかった。
前へ 次へ